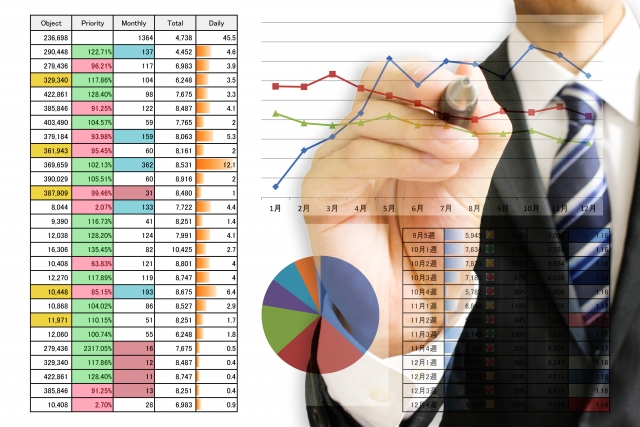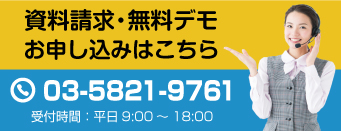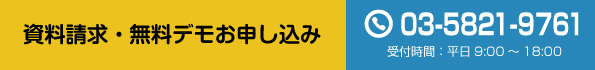営業支援ツール・SFAで営業マンの業務を効率化!主な機能と導入時の注意点
黙ってモノが売れる時代は、遥か昔のことです。とはいえ、闇雲な飛び込み営業で一日何十件も回ることは得策とは言えません。もはや体力&出たとこ勝負で営業する時代ではないのです。
市場をきちんと見据え、そこにいる顧客との関係性を強化し、その顧客が欲しているだろう商品を投入すれば、バンバン売れます。理屈としてはそうなのですが、そううまくいかない理由の一つに、競合の存在があります。
その競合を出し抜いて、自社の売り上げを伸ばすためには、顧客管理だけでなく、営業・商談のプロセスを可視化することが大切です。そのためにはITを活用した営業支援ツールが最適です。その営業支援ツールについてご紹介します。

営業支援ツール(SFA)導入の目的
営業支援ツール(SFA)とは?
Sales Force Automationの頭文字を取って「SFA」と呼ばれており、日本では「営業支援システム」と訳されています。
営業支援ツールを導入する目的
営業支援ツールを導入する目的として、第一に営業担当者の業務を効率化して受注率を高める。第二に案件の進捗状況や商談の内容、契約の見込み、担当者のスケジュールなどの情報を視覚化する。
そして第三として営業のノウハウを共有することが挙げられます。
営業支援ツールが普及した背景
1990年代にアメリカの企業で導入が始まったとされています。営業活動は属人的になる傾向があり、獲得した名刺や取引先との商談の内容、営業ノウハウなどは人への依存度が高いため、営業マンの入れ替わりによって、営業スキルの水準が下がったり、取引先との関係性が崩れたりすることが多々ありました。
それを防ぐためSFAを導入することによって、案件情報を共有し、効率的に営業活動を行えるようにしたのです。
それまでは、紙やExcelで情報を管理しており、入力や管理に手間がかかっていたのですが、IT技術の発展により、営業に必要な情報を一元管理できるSFAが登場。
さらに、クラウドが浸透することで、低価格で機能的なツールが利用できるようになり、広く利用されるようになったのです。
営業支援ツール(SFA)の主な機能
顧客管理
商談の状況、訪問履歴など過去の実績も含め、顧客ごとにアクションを管理します。
誰がキーマンであるかも管理し、起案者、決裁権者はもちろん、顧客ごとに決裁までのプロセスも管理します。
行動管理
日ごと、週ごと、月ごとに営業マンの行動予定と実績を管理します。そうすることで、特定の顧客、特定の地域に偏ることや、効率的な営業マンの移動も分析することが可能となります。
日報・営業報告作成
営業マンが顧客を訪問し、どのような営業活動をおこなったのかを可視化するための機能。そこには案件の金額、売上確度、クロージングの予定が記載されています。
請求書・見積書作成
商品番号、数量、相手先を入力すると該当する商品の情報を商品データベースから自動的に取り込んで、請求書や見積書の作成が簡単に行えます。
売上管理
営業日報に記載された案件金額を集計して売上管理として見ることができます。実績はもちろん、売上確度とクロージングの予定ごとにも見ることができますので、どの案件がいつクロージングして売上として計上できるのかを会社全体あるいは営業マン個人単位で管理することができます。
スケジュール管理
営業日報を参照して商談のプロセスをスケジュールという形で見える化します。そうすることで、クロージングにむけてのスケジュールが可視化でき、いわゆる、ほったらかし商談が出るのを防ぐことができます。
To Doリスト
クロージングにむけて商談のステージが上がってくるとやるべきことが増えてきます。次は見積もりを出すのか、それとも再度提案が必要なのか、いくつもの案件に関わっている営業マンにとっては重要かつ必要な機能です。
データ分析
自社製品が引き合いからクロージングまでどれだけの期間要しているのか、あるいはどの商品の販売サイクルが早いのかなどデータ分析することで今後の営業活動や商品開発に役立てることができます。
商談プロセス管理
部下・課員の案件一覧と商談進捗度合いを一目で把握しできます。その中で、停滞している案件やアドバイスすべき案件には的確な指示を与え、共有すべき商談事例については商談経緯の情報共有を指示することができます。
営業支援ツール(SFA)導入のメリット
営業支援ツール(SFA)導入時に気を付けること
営業担当者の業務内容を可視化できる
会社の視点から見た場合、営業マンの1日の業務内容やスケジュールを確認することは労務管理の観点からも大切なことです。営業支援ツール(SFA)の導入は、労務管理ということに加えて、マネージャーが営業担当者を管理しやすくなり、結果タスクの抜けや漏れをなくすことができます。営業マンの動きが可視化できることでタイミングよく適切な指示を与えることが可能となります。
営業担当者の仕事を効率化できる
顧客情報の確認、商談内容の報告、スケジュールや日報、見積書の作成という営業マンに必要な作業が一つのツールで行えるのも営業支援ツール(SFA)導入メリットの一つです。SFAさえ開けば、営業に必要な情報をほぼ全て確認できるようになるのは、営業活動の効率アップにつながります。
情報の共有・分析ができる
案件の進捗状況や問題点などをリアルタイムに把握できることは管理者にとってとても大切なことです。自分の部下の仕事の進捗を知ることで、リスクに備えられるだけでなく、作業の遅れによるクレームへも早期に対処することができます。
特に人気商品などは営業間で奪い合いになりますから、商品データベースと照らし合わせながら、欠品を未然に防ぐことも可能となります。
また成約率や売上見込みを基にレポートを作成できるため、マンスリーレポート作りも容易となります。
営業スキルの向上を図れる
営業支援ツールの本来の目的は、営業プロセスの可視化にあります。それができればl営業プロセス優秀な営業マンが取っている行動を共有することができ、新人営業マンへのOJTツールにもなります。資料作成の方法や商談後のメール内容、フォローの仕方など営業担当者間でノウハウを共有することで、営業スキルの底上げが可能になります。
営業支援ツール(SFA)導入時の注意点
解決すべき課題を把握する
営業支援ツール(SFA)を導入する前に、まず自社でどのような課題があるのかについてきちんと棚卸する必要があります。棚卸作業から詳らかになった課題を解決するためにはどのような機能が必要かを考えてみると良いでしょう。必要な機能を過不足なく備えるツールが好ましいのは言うまでもありませんが、機能が少なすぎると課題を解決できず、多すぎると持て余すということになりますから、まずは、自社が持つ課題を明確にすることから始めます。
導入による営業担当者の負担を考慮する
自社の課題を明確にせず、闇雲に営業支援ツールを導入してしまった結果、陥りやすいのが営業担当者の負担が増え、逆に営業効率が下がってしまった、ということです。
どんなに優れた営業支援ツールでも、個々の営業マンがツールの使い方を覚える時間が必要となります。
その辺の手間、工数もきちんと考慮しなければなりません。
操作方法が複雑だったり、入力項目が多すぎたりすると、かえってストレスになる可能性があるため、作業効率が落ちてしまわないように注意する必要があります。できるだけシンプルに運用できるツールを選ぶことが肝要となります。
費用と効果のバランスを確認する
課題の解決ができて、これだと思う営業支援ツールに出会えたとしても、月額の費用がかさんでしまうと継続的に利用することが難しくなります。
現在はクラウド型の営業支援ツールが主流ですが、利用する人数や期間によっては、自社内にサーバを構築して運用するオンプレミス型の営業支援ツールのほうが経済的な場合があります。
一度導入するとすぐに変えることは難しいですから、費用対効果を検証して、長期的に利用でき、かつ課題を解決できるツールを厳選することが大切です。
そのためには、複数候補をたてて、費用と効果において納得がゆくまで、比較検討することです。
本格導入の前にトライアルを行う
しっかり検討して厳選して導入したつもりでも、ツールが定着せず、期待した効果が得られなかったという話はよく耳にします。
本格導入する前に、少数の営業担当者にテスト利用してもらい、使いやすいか、どれだけの効果があるかなどしっかりヒヤリングし、運用にあたっての課題を詳らかにします。それら課題を解決できたのち、全社での本格導入することをお勧めします。
中には、一定期間無料でトライアル利用できる営業支援ツールもありますから、そのようなサービスを積極的に利用してみるのが良いでしょう。クラウド型ならまだしも、オンプレミス型で導入した後だと簡単にやめることはできなくなります。
営業支援ツール(SFA)「NICE営業物語」の特長
<営業現場の声を反映して開発されました>
NICE営業物語は、日本固有の営業スタイルに合わせて開発され、実際に運用される方の意見や要望をもとに機能拡張を行っています。モバイル対応、クラウド環境での提供のほか、お客様のスタイルに合わせて入力、出力などのフォームをカスタマイズできるなど、柔軟性・拡張性の高い営業支援ツールとなっています。
<入力・検索フォームを自由にカスタマイズできるd Btool>
dBtoolは、Webブラウザ上で入力フォームや検索フォームなどを自由に作成することができる、Webデータベース作成ツールです。dBtoolを使用することで、NICE営業物語の各種標準フォームをお客様の営業スタイルに合わせて自由にカスタマイズし、新しくデータベースを作成して自由に情報管理を行うこともできます。簡単な操作で、HTMLやデータベースの知識がなくとも作成できます。
<カスタマイズでオリジナル機能や他のシステムとの連携が可能です>
「自社の業務フローに合わせて仕様を変更や機能追加したい」「現在利用している基幹システムとの連携を図りたい」といったご要望には個別にカスタマイズすることで対応できます。
さらには、他社の名刺管理システムや地図検索サイト、グループウェアとの連携にもカスタマイズ対応しています。
主な機能
<営業報告作成機能>
報告書作成はいつでも面倒なものです。ましてや手書きの報告書はなおさらです。NICE営業物語の報告書作成機能は入力フォームを極力シンプルにしています。さらにスマートフォンなどのモバイル端末からも入力できますので、これらを活用すれば訪問先や移動の際の空き時間を利用して営業報告書を作成することができます。作成した報告書はすぐに送信できますから、上長やグループ内へリアルタイムに通知することができます。
<営業担当者ポータル機能>
スケジュールや実績など、営業担当者が必要とする情報を一画面で把握できます。また、タイムラインで流れてくる他の営業担当者の商談事例や、日々の活動に対する上司からのコメントを確認できたり、自動で通知される警告メッセージにより、対応が遅れている案件などを確認することができます。
さらにクラウド型のNICE営業物語であれば、いつでも、どこでもアクセス可能ですから、必要な情報をいち早く把握することで、商機を逃すことがなくなります。
活用シーン例
営業支援ツールの活用例を未導入の会社と導入済みの会社との比較によりご紹介いたします。
<営業支援ツール未導入A社>
朝礼が終わって、それぞれの営業マンは上司にたいして、昨日の営業報告をし、続いて継続中の案件や本日訪問予定の会社などを申告します。それだけで1時間以上を有します。それが終わると営業マンは各々の営業現場へと出かけて行きます。そして17時半すぎ、帰社した営業マンたちはその日の営業日報を作成します。訪問先、面談相手、商談内容、案件金額、商談確度などを記入します。
それをプリントアウトまたはメールで上長に提出して業務終了。時計はすでに20時。今度は上長が各営業マンから提出された営業日報を確認しながら案件内容確認し、Excelで集計します。そうしているうちに上長の退社時間は21時あるいは22時となってしまいます。その時間だと、すでに営業担当役員や社長は退社していますから、その日のうちにA社の営業活動がどうだったのかなど経営者層は知ることはできません。その結果、毎朝、朝礼のあと営業マンから逐一報告を受けることとなり、それが営業マンの外出時間を遅らせるという悪循環となっているのです。
報告書提出や集計、分析が翌日以降となることで、もしかするとA社は大きな機会損失があるのかもしれません。
<営業支援ツール導入B社>
朝礼の後、B社の営業マンたちは一斉に会社を飛びだしていきます。中には、客先へ直行している者も数名います。商談が終わり、次の訪問先まで移動時間がある営業マンは、駅のベンチに腰かけて、次の電車を待つ間、スマートフォンを取り出しで、さきほどの商談の報告です。訪問先、面談相手、商談内容、案件金額、商談確度などの必要項目を入力し、送信ボタンを押せば完了。そして次の訪問先へと移動。17時、最後の訪問先での商談が終了。位置的に帰社するよりも自宅のほうが近い。当然直帰です。でもその前に、さきほどと同じようにスマートフォンから必要項目を入力して送信すれば、本日の営業報告はすべて完了。
一方会社では、上司が営業支援ツールを見ています。すでにそれぞれに営業マンから一日の報告が送られてきているので、すべての商談の進捗や商談確度の状況、今月どれくらいクロージングできて、達成率はどれくらいなのか、部門ごと、個人ごとにリアルタイムに集計作業を行っています。時計を見ると17時。定時に帰社できそうです。
営業支援ツールにて集計された商談情報は、上長だけでなく、同じグループや役員、社長へもリアルタイムに通知できますので、緊急性を要する案件が生じた場合も、機会損失することなく対応することが可能となります。
営業支援ツール(SFA)は営業マンの「働き方改革」につながります。
営業支援ツールを導入したからと言って、翌月から極端に売り上げが伸びるということはありません。
また、営業支援ツールは営業マンの労務管理ツールでもありません。営業マンが怠けてないか、外出先で遊んでいるのではないか?というのをチェック、監視するためのものでもありません。
営業支援ツールは営業マンの生産性を最大限に向上させ、結果、営業マンの本来のミッションである営業活動に専念させるためにあるのです。
案件の発掘からクロージングに到るまでの商談プロセスを可視化することにより、効率よく営業マンが動けるように支援するのが営業支援ツールの役割なのです。
その結果として、モバイル端末でどこからでも報告書を送れることが直行直帰を実現し、営業マンの「働き方改革」につながっているのです。
営業支援ツールにより営業マンが楽しく仕事ができる会社は売上向上が大いに期待できると確信しています。