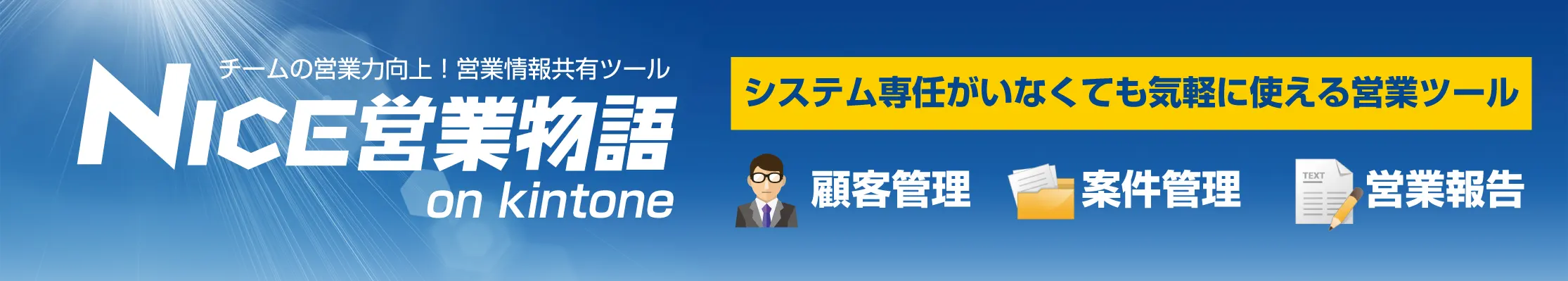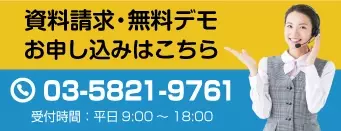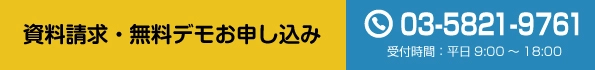SFA導入に失敗する理由や解決策をわかりやすく解説

SFA(Seles Force Automation)は顧客情報や案件進捗等の一元管理を実現するITツールであり、営業支援システムとも呼ばれます。SFAを導入する大きなメリットは営業活動の「見える化」です。今まで営業担当者が個々に管理されていた情報をシステム上で可視化・共有することにより、営業フローの最適化が図れます。
一方、SFAを導入したものの、システムを十分に活用できず業務フローの改善に失敗してしまうケースも少なくありません。SFA導入の際は事前に十分な調査を行い、自社が求める機能を明確にしておきましょう。この記事ではSFAの導入に失敗してしまう理由や、失敗を回避するためのポイントを解説します。
SFAの導入に失敗する理由
「SFAを導入したにも関わらず社内に定着しなかった」という事例は決して少なくありません。ここでは企業がSFAの導入に失敗してしまう主な理由を解説します。
SFAの導入目的があいまい
SFA導入に失敗する主な理由のひとつが「ツールの導入目的があいまいであること」です。SFAはあくまで手段であり、十分な成果を上げるためには使う側が明確なゴールを定めて運用しなければなりません。単にSFAを導入しただけでは自社が解決すべき課題にアプローチできずに終わってしまう恐れがあります。
操作が複雑で使い勝手が悪い
SFAの操作が複雑であったり、使い勝手が悪かったりすると、従業員の利用率は伸びていきません。「操作のわかりやすさ」や「使い勝手の良さ」はSFA導入の成否を左右する重要な要素です。新たなツールの導入には従業員の負担やストレスを増大させるリスクもあることを覚えておきましょう。
製品の精査が不十分
機能の精査が不十分な状態でSFAを導入してしまった結果、後々になって「必要な機能がない」といったトラブルに陥るケースも見られます。SFAは製品によって機能が異なるため、必ずしも全ての製品が自社で有効活用できるとは限りません。他社の評判や販売実績のみで製品を評価してしまうと、自社にマッチしない製品を選んでしまうリスクが高まります。
SFAを用いた業務フローが確立されていない
SFAを導入しても、共通の業務フローが確立されていなければシステムの有効活用は望めません。ITツールの取り扱いは人によって得手不得手があり、SFAの使用方法を個人に一任していると、営業担当者ごとでシステムの利用頻度や活用度合いに差が生じてしまいます。また、全ての営業担当者が一様にSFAを運用しなければ、SFAのメリットである情報の一元化も不十分なものとなってしまいます。
蓄積されたデータを分析・活用できる人材がいない
SFA導入の効果を最大限発揮するためには、システムに蓄積されたデータの分析や活用ができる人材の配置が不可欠です。システムに蓄積されたデータを活用して業務フローの改善や成約率の向上といった成果に結びつけられなければ、SFAの導入に成功したとは言えません。
蓄積されたデータを基に、顧客管理の徹底や営業力の底上げを図ることがSFAの本質です。SFAの導入に合わせ、データ分析ができる人材を配置する、または営業担当者個々にデータ分析の方法を身に付けさせるなどの対策を講じましょう。
SFA導入の失敗を避けるためのポイント
社内にSFAを定着させるためには、導入後のビジョンを明確にしたうえで計画的に運用することが大切です。ここではSFAの導入失敗を避けるためのポイントを解説します。
解決すべき課題や導入の目的を明確にする
SFAの導入に際しては製品選定の段階で自社が解決すべき課題や導入の目的を明確にしておくことが大切です。予め自社が解決すべき課題を洗い出し、その解決に必要な機能を絞り込んでおきましょう。SFAを導入することを目的にするのではなく、SFAによってどのように業務改善を実行するかを考えることが重要です。
営業担当者の理解と協力を得る
SFAの運用を定着させるためには、実際にシステムを運用する営業担当者の理解と協力が不可欠です。そのためには自社が抱える課題やSFAを導入する目的を、営業担当者と共有する必要があります。
会社が新たなシステムを導入する場合、それに対して心理的な抵抗を覚える従業員も少なくありません。しかし、そのシステムが有用なことがわかれば、抵抗感も薄れ好意的に捉えてくれるようになります。管理者が営業担当者に一方的にSFAの運用を押し付けるのではなく、その有用性を理解してもらえるまで根気よく説明することが大切です。
運用マニュアルを作成する
新たに導入したSFAを想定通りに活用するため、営業担当者に向けた運用マニュアルを作成しましょう。また、運用マニュアルは一度作成して終わりではなく、常にPDCAを回して随時改定していくことが大切です。運用マニュアルの完成度を高めていくことで、新規配属の営業担当者もスムーズに業務を開始できるようになります。
スモールスタートで入力の負荷を軽くする
新たにSFAの運用を開始する際は一部の機能に限定したスモールスタートを心掛けましょう。多くの機能を持つSFAは、初めから全ての機能を利用しようとすると現場の作業量が増え、実務に支障をきたす場合があります。SFAの運用は優先度の高い機能から開始し、営業担当者のシステム習熟度に合わせて徐々に機能の範囲を広げていきましょう。
失敗しないSFAツールの選び方
SFAの導入を成功させるためには自社に適した製品を選ぶことが何よりも重要です。ここではSFAの製品選定をする際に注意すべきポイントを解説します。
営業担当者の目線で製品の選定を行う
SFAを選ぶ際は必ず営業担当者の目線で製品選定を行いましょう。実際の業務においてSFAを活用するのは主に現場の営業担当者です。コスト面や機能面が優れていたとしても、現場の社員が使いにくいと感じてしまえば、システムの定着には至りません。システム選定者は必ず営業部門から意見を聞き取り、現場が望む機能を把握するようにしましょう。
APIによる他ツールとの連携は可能か
企業向けのITソリューションではAPIによる他ツールとの連携も重要な選定項目となります。SFAの場合、近年特に注目されているのがMA(マーケティング・オートメーション)との連携です。SFAの顧客情報とMAの機能を連携させることにより、無駄のない効率的な営業活動が可能となります。
ベンダーのサポート体制を確認する
SFAの運用をより効果的に行うため、ソリューションを提供するベンダーのサポート体制も確認しておきましょう。システムの保守や遠隔サポートはもちろん、ベンダーによってはSFAを有効活用するためのセミナーを開催している場合もあります。サポート体制が充実したベンダーの製品であれば、中長期的に営業力の強化を図ることができます。
【まとめ】
SFAは目的を明確にして導入しよう
SFAの導入に失敗してしまう要因としては、導入の目的があいまいであることや、現場のニーズを把握できていないことなどが挙げられます。コストを無駄にしないためにも、予め営業担当者と意見交換を行ったうえでSFAの製品選定を行うようにしましょう。
なお、SFAの選定にお悩みであれば営業支援システム「NICE営業物語 on kintone」の利用をご検討ください。「NICE営業物語 on kintone」では必要な機能を選択してご利用いただけるだけでなく、APIによる他システムとの連携や機能拡張も可能です。自社に最適なSFAが見つからないとお悩みの際は、ぜひ「NICE営業物語 on kintone」をお試しください。
#SFA #失敗