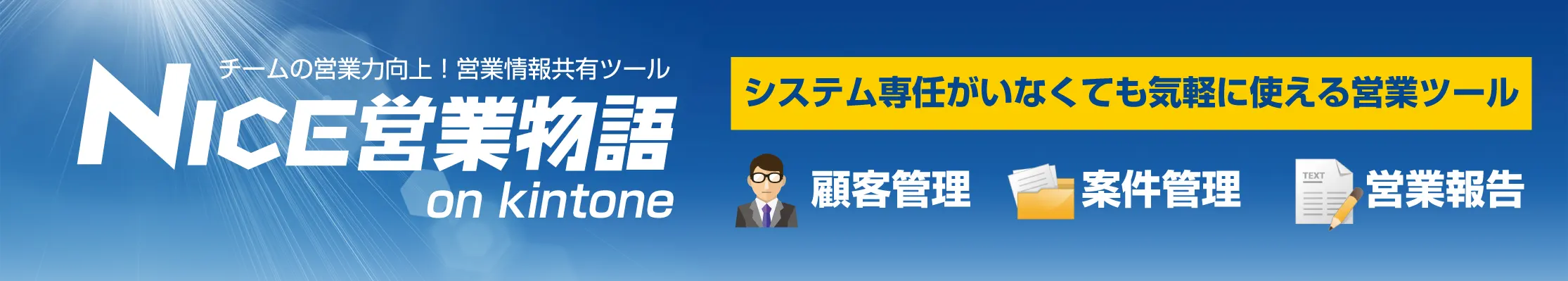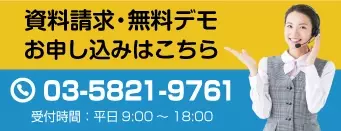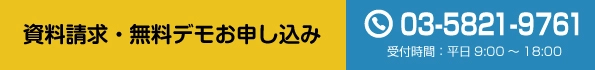SFAが定着しない理由とは?定着させるポイントを徹底解説

SFA(営業支援システム)を導入するだけでは効果を発揮できません。実際に日常業務で活用されてこそ真価を発揮するものです。
しかし、システムが定着しない理由には、操作の難しさや、入力項目の多さ、サポート体制の不備など、さまざまな要因があります。
この記事では、SFAが定着しない理由とその解決策を、運用中の場合と乗り換えを検討する場合に分けて解説します。
SFAは定着させてこそ真価を発揮する
SFAの本当の価値は、システムを導入すること自体ではなく、営業プロセスを効率化し、データに基づいた営業活動を実現することにあります。
システムを定着させるポイントは、データの蓄積とその活用です。営業活動に関するデータを正確に集め、これを分析して活用することで、SFAの価値が最大限に引き出されます。さらに、営業プロセスの可視化や標準化が進むため、組織全体の営業活動の質を向上できます。
しかし、営業担当者が日常的にツールを使いこなさなければ、データが蓄積されず、効果も十分に発揮されません。SFAは、日常業務に組み込み、現場に定着してからこそ有効なツールとして機能するものなのです。
SFAが定着しない理由
導入することで様々なメリットを享受できるSFAですが、導入してもさまざまな理由で定着しない可能性があります。ここではSFAが定着しない主な原因について解説します。
SFAの必要性が伝わっていないから
SFAが現場に定着しない理由の一つは、その必要性が十分に伝わっていないことです。経営陣や管理者だけが理解していても、現場の担当者がその価値を感じなければ、入力や活用に時間をかけようとは思いません。
まず、自社の課題はっきりさせることが重要です。そのうえで、導入目的が顧客管理なのか、営業進捗の管理なのかを明確にし、そのメリットを現場の担当者にしっかり説明します。SFAは担当者の営業活動をサポートするツールであり、監視のためではないと伝えることが、現場での積極的な利用につながります。
使いづらいから
現場の担当者にとって使いづらいものは定着しづらいです。機能が不足していると、現場のニーズに応えられず、活用が進みません。
機能が多すぎても、システムや操作が複雑になり、営業担当者が使いこなせない場合もあります。使いづらいツールを使い続けることは、期待した効果が出づらい上に、担当者のモチベーション低下につながるリスクもあります。
この問題の発生を防ぐためには、自社のニーズに合った、シンプルで使いやすいシステムを事前に検討することが必要です。
項目が多すぎるから
入力項目の多さが営業担当者の負担になっている可能性があります。営業活動において、案件や顧客情報を詳細に記録するのは大切です。しかし、入力項目があまりに多すぎると、担当者の業務負担が大きくなり、次第に利用されなくなります。
また、入力項目が多いだけでなく、スマホからの入力ができなかったり、他のツールと連携できなかったりする場合も、利用を避ける要因になります。
運用体制が整備されていないから
社内の運用体制が整っていないのもSFAが定着しない理由の一つです。ITのリテラシーは従業員によって個人差があるため、ITに苦手意識がある人はツールの使用を避ける傾向があります。
SFAは営業組織の改善が目的なため、一人でも使用しない従業員がいると正確な情報収集や改善ができなくなります。このような事態を防ぐためにも、ツールを導入する前に社内の運用体制の整えておくことが重要です。
ベンダーのサポートが不十分だから
SFAが定着しない理由として、ベンダーのサポート体制が整っていないことが考えられます。運用中には疑問や課題が生じるのは避けられません。サポートが不足していると、ユーザーは問題を解決できず、SFAの利用を諦めてしまう可能性があります。
サポートが充実していれば、適切な解決策を得られたり、自社の営業プロセスに合ったベストな活用方法を知れたりするメリットがあります。
運用中のSFAを定着させるには?
SFAの定着化には原因に合わせた対策が必要です。ここでは現在運用中のSFAを定着させるための対策を紹介します。
現場にSFAの導入目的やメリットを伝える
現場の営業担当者に導入目的やメリットをしっかり伝えましょう。目的が共有されていないと、営業担当者はSFAを使う意義を理解できません。
特に、経営層が現場の声を無視して導入を決定すると、営業担当者から不満が出る可能性があります。こうした事態を避けるために、導入前にしっかりと目的を共有する時間を作り、理解を深めてもらうことが大切です。
導入目的を現場担当者に説明する際、自社が抱えている課題も合わせて伝えることで、より納得してもらいやすくなります。無料体験期間がある場合、営業担当者にSFAを使ってもらうのも効果的です。
運用体制を整える
SFAの運用体制やルールを整えます。部門ごとの役割や管理者の設定、入力方法の統一、操作マニュアルの準備、トラブル対応の窓口など、必要なルールをシンプルにまとめ、実際に運用しやすい体制を整えましょう。
SFAは営業部門だけでなく、他の部門ともデータを共有することで効果を発揮するため、全体での協力体制を築いていくことが必要です。
入力項目を必要最低限に絞る
入力項目を最低限に絞ります。入力項目が多すぎると、現場の負担が増え、業務に支障をきたす可能性があります。そのため、必要な項目をあらかじめ整理し、最小限に抑えることがポイントです。
入力する項目は、次のような観点から絞ります。
- 顧客分析に必要な情報か
- KPIの分析に必要な情報か
- 関連部署にも必要な情報か
- 営業戦略を考えるうえで必要な情報か
いずれ役に立つかもしれないからと活用目的が不明瞭な項目は除外し、入力する情報が具体的に何に役立つかをはっきりさせましょう。このように、現場担当者が作業の重要性を理解させることは、SFAの定着にもつながるのです。
ツールの利用状況を社内評価の基準に組み込む
SFAの利用状況を社内評価の基準に組み込むという方法もあります。例えば、営業会議で使用する情報をSFAのデータに限定すると、他のツールで管理していた情報は正確なものと見なされなくなります。
これにより、自然と営業担当者はSFAへの入力を習慣化していくでしょう。一見、強制的な手法に思えるかもしれませんが、結果としてSFAに全ての営業情報が集まり、データの一貫性や正確性が保たれるため、営業活動にとっても有益なシステムになります。
定着しやすいSFAに乗り換える場合
運用中のSFAを定着させる対策を行っても、なかなか改善が見込めない場合、乗り換えを検討するのも一つの手段です。
ここではSFAの乗り換えを検討する際に押さえておきたいポイントについて解説します。以下のポイントを押さえることで、SFAの定着率を高められます。
現在運用中のSFAの課題を洗い出す
SFAを乗り換える際には、現在のツールの課題をしっかり洗い出すことが大切です。成果が出なかった理由を把握していないと、乗り換えても同じ問題でまた躓く可能性があります。
運用に失敗した原因が明確になれば、自社にとって必要なSFAの条件がはっきりしてきます。この工程は、実際にツールを使っている現場担当者と一緒に行うことで、現状をより正確に把握しやすいです。
情報収集をしっかり行う
より自社に合うツールを導入するためには、情報収集が欠かせません。インターネットや展示会などを活用し、複数のSFAツールを比較検討しましょう。機能面、サポート体制、価格、導入実績などを確認し、自社に最適なツールを見つけるために、無料トライアルを利用して実際の使い勝手を確かめるのも有効です。
また、収集した情報は表にまとめたり、点数化したりすることで視覚的に整理しやすくなります。
導入するツールの選定基準を決める
導入するツールの選定基準を明確にしましょう。基準を決める際に、定着しやすいSFAの特徴を把握しておくと、現場での活用が進みやすくなります。定着しやすいSFAの特徴は以下の通りです。
- 他のシステムと連携ができる
- カスタマイズの柔軟性が高い
- サポート体制が充実している
定着しやすいツールには他のシステムとの連携ができるという特徴があります。連携製品が豊富で、将来的な機能拡張がしやすいツールを選びましょう。
カスタマイズの柔軟性も考慮すべきです。標準パッケージで対応できない要件が発生する場合、カスタマイズができるかどうかが自社の運用に影響します。
特にクラウドベースのSFAでは、個別開発やバージョンアップに制約があることがあるため、事前に確認しておくことを推奨します。
サポートの質も必ずチェックしましょう。SFAに限らず、新しいものを取り入れる時は、操作や機能に関する疑問は多く出てくるものです。しかし、サポート体制が十分でないと、問題が出た時すぐに対処できません。
例えちょっとした問題でも、解決に時間が掛かる、SFAを使うことへの心理的ハードルが高くなってしまうことがあります。一方、現場で問題が発生した際にすぐ対応できるサポートがあれば、SFAの運用はスムーズに進み、現場での定着も進みやすくなります。
以上のポイントを理解した上で、インターネットや展示会で情報を収集し、機能やサポート体制、価格、導入実績などを比較検討しましょう。
現場の担当者と一緒にツールを選ぶ
リプレイスを行う際は、必ず現場の担当者を巻き込みましょう。現場の理解と協力が得られれば、導入に対する抵抗が減り、スムーズな導入が期待できます。
また、経営陣だけで進めるよりも、現場の意見を反映させやすくなり、実際に使いやすいSFAを選べます。さらに運用が始まった後に出てくる疑問や問題にも、対応できる体制を整えられるのも大きなメリットです。
このように、現場を巻き込むことで、SFAの導入から定着までをスムーズに進められるようになります。
まとめ
今回はSFAが定着しない理由と、対処法を状況別に解説しました。SFAは、現場に定着して初めて機能するものです。せっかく導入しても、使ってもらえなければ意味がありません。システムの定着にしない原因を突き止めて、それにあった対策を講じることが大切です。
対策を講じても改善が見込めない場合、乗り換えも検討しましょう。乗り換える時は、現場の担当者も巻き込んで、現場にとって使いやすいツール選びを行うことが大切です。
SFA・営業支援システム「NICE営業物語 on kintone」は、複数のシステムとの連携が可能で、外出先でも入力できるなど、現場での使い勝手を考慮した設計がされています。
さらに、訪問とオンラインでの無料デモにも対応しているため、自社にとって使いやすいかどうかを確認できます。営業管理をより効率よく行いたい方や、運用中のSFAからの乗り換えを検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
#SFA #SFA定着 #kintone