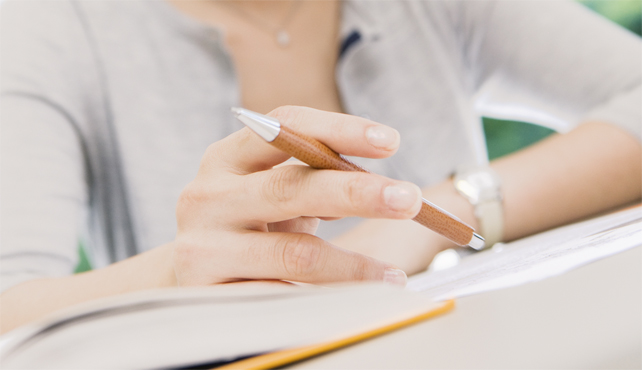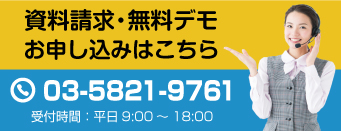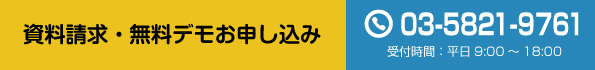ピンチをチャンスに!営業のクレーム対応術
クレーム処理は、数ある業務の中で最も重要なものに値するでしょう。このときの対応によっては、会社全体を揺るがすような大事になる恐れもあります。逆に、クレームにきちんと対応することができれば、会社に対する印象も良くなることは間違いありません。今回の記事では、営業のクレーム対応の基本と、より大きな信頼に変えるテクニックをお伝えしていきます。

クレームはチャンス!より大きな信頼を勝ち取る機会が与えられたと思うべき
まず前提として、「クレームを言う人は、会社に期待している人」という考えを持つべきです。誰しも好きで争いたいわけではありません。もし、「この会社ダメだな」「この営業に言っても無駄だな」と思っているならば、何も言わずに去っていくものです。
クレームが来たということは、クレーム部分さえきちんと対応してくれれば、継続して付き合いたいと思っているということ。つまり、クレームをもらった時は、信頼を回復するチャンスなのです。しかも対応によっては、信頼の回復だけでなく更なる信頼感が生まれることでしょう。
なぜクレームを言ってくるのか?相手の気持ちを考える
まず、なぜクレームになったのかを考えます。クレームには、人に対して、商品や契約に対して、会社に対してなど、さまざまな種類があります。これを見誤ってしまうと、間違えた対応になってしまいますので、注意が必要です。クレームを言う人は、頭に血がのぼってしまい話がまとまらない場合もあります。お客様の気持ちになり、何に対してクレームを言っているのかをお話の中から読み取ることが、最初の段階になります。
賢いクレーム対応の手順とは?
クレーム対応は、以下の2点が課題になってきます。
- 相手が望むことをする
- 妥協点を見つける
そのための手順は、以下の通りです。
- クレーム対するお礼を言う(電話をいただき、わざわざお越しいただきありがとうございますと、自分たちの会社のために手間をかけてくれたことに対してお礼を言います)
- 誠意を持って謝る(基本中の基本です)
- 相手の話を最後まで聞く(途中で遮らない、「しかし」などの反意語は使わない、言い訳はしないのがポイントです)
- 何をして欲しいのかを探し出す、聞き出す(お客さまの口で言ってもらうのがベストです)
- 上司と共に再度謝り、どうしてミスが起きたのかをきちんと説明する(再発防止策なども提案します)
- 相手が望むことができるようだったら対応し、できないようだったら、妥協案を提案する(そのクレームに見合った対応をすることがポイントです)
- 交渉が決裂しても、5.6を繰り返す(最初は怒りで許してもらえないかもしれません。しかし、時間が経ち、冷静に考えてもらえば分かってくれることが多々ありますので、1回で諦めないことです)
自分は悪くない……理不尽なクレームの場合はどうする?
ほとんどの人は、営業担当者に期待を込めてクレームを言い、必要以上の要求はしてきませんし、話せばきちんと分かってくれることも多いです。しかし、稀に理不尽な要求やクレームを言ってくる人もいます。このときの対応によっては、大きなもめごとに発展してしまう恐れがあるので注意が必要です。そうなってしまうと、双方にとってメリットはありません。対応をするときのポイントとしては、
- 謝る(まず、事態が起こってしまったことについてはきちんと謝罪をします)
- 毅然とした態度をとる(理不尽な要求に対しては、毅然とした態度で断ります)
- どうしてこのようなクレームになったのかを考える(何がクレームにつながったのか原因を特定します。また、自分たちが本当に悪くないのか、ミスが無かったのかをよく考えます)
- 対応策は最低限に抑える(譲ってしまうと、相手にとってメリットが大きくなってしまいます。最低限の対応策で納得してもらうようにします)
- 感謝の気持ちを持って丁寧に対応する(いくら理不尽なクレームを受けたとしても、相手はお客様です。営業の態度によっては、怒りが増長してしまう場合があるので注意が必要です)
営業担当者がクレーム対応をする場合、誠実な態度と改善策を提案することで、信頼を回復することは可能です。営業担当者が「面倒だな」と思っていると、相手は敏感に感じ取りますので、誠意を持って対応できるようにしましょう。